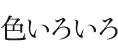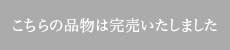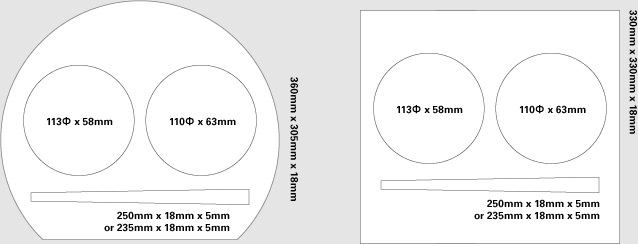![]()
よく見かける黒や朱の漆器は、木地である「木」を見せない手法で、下地を整える為に多大な労力をかけている。かたや飛騨春慶は、性能として十分なだけの漆を塗り、木地の木目を生かした潔い漆器だ。潔いといっても手を抜いている訳ではない。木地が見える為に下塗りに豆渋で黄色く染め、拭き漆を幾度か重ねて、その後に漆と油を混ぜて塗り重ねた合理的な手法だ。春慶の下塗りには黄色の他にも紅や黒など様々な色があるが、この黄色は透けて見える木地に深みを出して木の色との相性も良い。だから黄春慶が主流になったのではないかと勝手に思っている。そこで、春慶の特徴である下塗りを再考して新たな色を探してみた。椀木地の燻煙乾燥の現場では、真っ黒に煤けた空間に出会った。壁や天井は煤でふかふかになっていて、この煤を下地に塗れないものかと塗師の滝村さんに相談をしてみた。その他にもお歯黒やベンガラなど幾つかの試みをお願いしたものの、なかなか良い仕上がりにならない。確かに永い春慶の歴史を思えば安易な試みなのかもしれないが、表現としての「春慶」ではなく、春慶の理由を知り新たな解釈が出来ないものかと模索した。